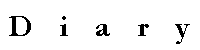
2月17日
小さな共同体としての近代
|
小さな共同体から始まっている。 自分から将来を考えることはやめてしまった。将来を見ても、黒い世界しか見えない。いずれはあらゆる所で破綻していってしまうと暗に感じている。自分の感覚で捉えきれないものが「外」だ。それに対して、自分の付近に「内」を作る。外のことを見なければいけないという目を大きく居直らせている。自分と、それを取り巻く過小な空間の中に和を求める。 「今」からの小さな時間の幅において、常に人との繋がりを求めている。今から取り残されることはこの上ない苦痛である。小さな共同体はそこに生まれる。人と人が集まっているときの、避けられない自我の衝突を最小限にくい止め、また他へ放出できるような逃げ道を確保するために機能する。複数の共同体に自分を表現しており、その相互には違う自分がいる場合もあるのである。 合わないと感じたらすぐに抜け出すことができる。不和を起こした共同体自身が新たな共同体を生む。その過程は誰が意識したものでもなく自然にかたちづくられていく。ひとまわりおおきな団体があり、そこに堅い枠があったとしても、その中にやはり生まれる。 社会は、無数の小さな共同体の総和として動いている。人一人よりも微妙に大きな単位のかたまりが外に向かって意見を発する。自分自身の意見でない意見は、妥当であるようなある一つのモノに従順になりやすくなる。一歩間違えば危険なモノに扇動されるかもしれないのである。 孤独への恐怖が絶えない限り、個人主義は成立しない。自分のしたいことは、動物本能的なものを除いて全て小共同体に吸収される。自我からの反発があるはずである。自分の意見が一瞬にして歪曲させられている。しかし、ここには気付かない。小共同体としての意見こそが自分の意見だと信じこんでいるからである。 とはいっても、この仕組みが良いと感じる。個々人の意見である「和」への暗の意識が、先の明るくない世界を歩み行く中で、悲観的にならない手段であるからである。人の性質として当然である装置といえば当然であるが、元々人が集合しているという時点で不可能である潰滅の回避に、全身全霊入ることを拒否することができるからである。小さな共同体は無意識にて良好である。 ***1999/8/30 社会学入門へのレポートより |
連絡板へ書き込む
DIARYのindex
Mameへはmame@sun-inet.or.jp