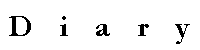
98年度
4月1日
再生
|
世の中は悲観的で様々な起伏が数多く起こっているけれども、なぜか心中は穏やか。まるで、天から見下ろすような心持ち。実際には色々と忙しく体をなげうっているのだけれど、それも白く淡く感じられて。映画のフラッシュの最後は画面いっぱいの白であるように、動乱が起こりすぎているときには、それから体の五感が遠ざかっていくのかもしれない。一面の白は、全ての最後。一面の白の後に、ただ太陽の光が射し込む光景が現れたならば、まだ続いている。また、壮絶な時間がかかるかもしれないけれど、個人の安らぎを求めて復興する。 個体と集団の矛盾は果てしない。矛盾は締めて破綻を来す。しかし、鋭利な頭でじらさせることはある程度出来ると思う。全てのルールはじらすための知恵ではないか。今日からまた再生と銘打って自らに幅を利かせる。 |
4月27日
作業
|
ジュケンセイとは、理性も感情も捨てたロボットになることか、もしくは、飴に釣られた幼稚園児になることかもしれない。黙々と"作業"をしているとそう思うことがある。特に、意義は十分に解っているはずなのだろうけれど、自らの興味からそがれかけているものに取り組む時というのは、どうしてもきちんと座っていられない。"普通"のことなのだと、とりあえず合理化して作業を進める。 とはいうが、快感に浸る教科もある。目の輝きは押さえきれ無く、多分無駄なことなのだろうが時間を多く費やしてしまう。好きなことをする時の体の欲望は止められないものである。 意味はどこにあるのか。自分が、この難しい数学や昔の文章を読むことになんの意味があるというのか。"ジュケンセイ"の称号を与えられた者にとって、このことに一度は疑問の念を抱いたはずである。 思い返してみると、私がはじめて学んだと感じた時というのは覚えていない。忘れたどころか、自分がこの世に生物として生まれたその瞬間から、学ぶことは始まっていると思える。小さい頃はというのは、まず学ぶ量というのが半端ではないし、親や他人から教わることに関してなんの疑問も抱かなかった。それが、成長していくに連れて、親からの学ぶことへの押さえつけを認識するようになり、ちょっとした防衛機制を働かせ、学ぶことも選ぶようになっていく。だんだん、合理化の技が冴えてくる。嫌なことも小手先で済ませてしまえるようになっているのだ。 そんな中で、自分の"好きなもの"とも出会っている。自分の好きなことをするというのは、満ちている瞬間である。嫌なことをどうにか避け好きなことをするという、逆らっていないずる賢さが増すのは当然である。 感情を割り切って直面したものを見ることはできないと思う。その上で、意味を探しても明確な答えは出てこない。人生の中で、最終的な"結果"は出てこないのだから、結果を知り得ない中で意味を探るというのは、あまり価値が無いと思う。自分を合理化する目的で、───この社会で自分のとりとめのない欲望をできるだけ開花させる目的で───意味を付け加えることには、価値があるかもしれない。 |
5月31日
対話
|
自分の弱さというのは、人に隠すべきものなのだろうか。自身の気弱な性格にこの問いのような思索をあてがい、試練を与え続けてきた。完璧主義の矛盾から生まれるわだかまりが、傲慢さは確固たる自分であるために必要だということを気づかせた。 自分にないものへの欲望は、気の強い前線に立つ人々への興味を駆り立てる。 それらの人々は、惜しみもない声量を発し、人一倍の頭のキレと、行動力を擁している。概して、自らの輪が大きく独創的な"自分"ができている。その自らの大きな輪の所為で他人が見えなくなりがちではあるが、間違いなく社会を先導している人々である。 私がそれらの人々に興味を駆り立てられる原因の欲望には、他人との対話(自己表徴)の快活さに惹かれているものがある。この社会で自己の確立を図るためには、他者との対話の快活さが重要な位置を占めていると思う。人間の理性がある限り、社会での自分の状態を認知できる意味で、対話は自分らしくあるための必要条件である。 しかし現代では、対話の方法が多様化し、その相互には不干渉なものが多い。そのために、小さな範囲でしか自分の状態を認知できなくなる場合がある。社会への適用範囲が狭い自分では、多くの時間を引き籠もってしまう。 多くの人に受け入れられるような自己を確立するためには、それらの人に共通な基本概念に則る対話が必要である。その上で傲慢で積極的な心構えによる、人それぞれに合った自己主張が必要となるのである。 |
6月30日
教育1.中教審の考え方
|
学歴偏重社会というのは、確かに問題である。一人一人の中の能力や適正をできるだけ有効に現せることができたならば、さまざまな分野での飛躍が期待される。また、親からの一方的な受験競争への参加を押さえれば、子供に、自ら学び、自ら考える機会が増えることもあろう。中教審が求める"「ゆとり」の中で「生きる力」を育む"という提言も、今までの形式的な平等の重視より起こる一元的な教育から、個性を重視した多元的なものへの転換をはかろうとしている。 しかし、教育とは本来、国家繁栄のために、またその一端を担う有能な人材を作るためのものである。個性的、創造的な人材を得るための「ゆとり」や制度の多元化は、一見奨励すべき方針に見えるが、そこまで単純ではないと思う。ゆとりを持った人々は、そのゆとりさ故に、かの社会主義国のように競争心を失い没落していく可能性もあるはずだ。 教育には二種類あると思う。単に知識を詰め込ませる無機的な教育と、今ある社会で生きていくための有機的な教育である。二種類のうち、戦後日本では選抜の指標に無機的な知識の優劣で判断してきた。国は、その判断基準だけでははかり得ない有機的な才能への指標を、創造的な人材を得るために改善しようとしている。また、その両極面の教育を充実させようとしている。 **この間、学校に提出した怪しい暴論です。特に改革案が練られていません。5回にわけて載せる予定です。 |
7月1日
教育2.個性の尊重への疑問
|
その改革のひとつである「個性の尊重」は大きな社会的不安を抱えることになるかもしれない。というのは、それが、精神が未分化な状態で教わるべき事柄ではないと思うことがひとつある。まず学ぶべきことというのは、有機的な教育の第一歩である「自己機制」だ。 精神が未分化の状態で、「個性の尊重」を教わることは、家庭外での子供のまわりにある抑圧対象を減らすことに繋がる。抑圧するものが減れば、自分のしたいことを押さえる必要もあまりなくなってくる。そして、この社会を外側から打破するならともかく(それは国の目指すところではないはず)、社会の規範に反した人材ができあがる。そのような人達は、高い自尊心故にいっそう人との繋がりを希薄にし、団結することさえできないだろう。 また、「個性の尊重」は日本が欧米型の社会を目指しているようにみえる。確かに、それは優れた人材の獲得になるかもしれないが、裏を返すと、国が必要としない低級な人をも増やすことになる。日本型社会構造の良い点は、貧富の差が激しくないところではなかろうか。それを、欧米に似せると、戦後日本では起こり得なかった、貧富の差や、犯罪の増加などが起こり得る。 義務教育期の教育は「個性の尊重」ではなく有機的な教育に焦点が置かれるべきである。そして、実践的に体感させるべきである。自分の才能がいくらあっても、今の社会のことが解っていなかったならばそれを活かすことはできない。「個性の尊重」は、高校生以降、小さなヒエラルキーの中で育んできた「生きる力」の土台の元で、はじめて自ら気づくはずである。 |
7月2日
教育3.家庭の変化
|
そうなると、以前の日本の教育の方が多少は良かったはずである。現在のこの問題には他に大きな原因が存在する。──それは、家庭の状況である。 今の小中学生あたりの親は、大まかにいわゆる「おたく世代」と言われた人々である。その世代の人々は、ひとつ上の団塊の世代によって少なからず放任され、自分と趣を同じにする小さなグループを生み出した。グループ間のネットワークはあまりなく、グループ内のみに常識を持った。それ故、独善的な意識を得る人も多かったと見る。 極端に言えば、自分の一人の子供に思いを馳せ、必要以上の干渉を行い、子供が自分で動くことを忘れているかのようにも見える。子供がした社会規範から外れる行為も、愛情過多な親からはもちろんきつく言われることなく、学校の先生からも「個性の尊重」のもと厳しく言われることがなくなっている。いわば、勉強はするものでなくやらされるもので、それに苦痛などの感情は生まれない。だから、この現状から、もう既に「ゆとり」は蔓延しきっている、ともとれる。 その上に、さらに「ゆとり」をつぎ足したならば、もう日本は行く先が見えない。「ゆとり」をつぎ足すと「生きる力」とともに無機的な知識までもが、五無主義のもと逃げていく。長期的に考えれば、小学校に有機的な教育へのヒエラルキーを復活させれば、初め親がとやかく言うかもしれないが、生徒自身が気づいて、今ある尺度からの飛躍が認められのではなかろうか。 |
7月3日
教育4.高校・大学選抜
|
この社会は高度に成長し過ぎているので、そこに手を伸ばそうとするとかなりの知識や技術がいることになる。有能な人材に不可欠なのはかなりの量の無機的な教育である。そこには、有機的な教育を妨げる大きな倒錯をはらんでいる。 現状は、「できる人」には無機的なものだけが富み、有機的なものはあまり冴えていなく、「できない人」はその逆の傾向にあると考えられる。理想は、その両方から教育をしていくということだ。 今の高校で各人は前述のような育てられ方のために、社会とは一線を隔絶した、自分とそのまわりの少数だけで構成する小宇宙内で自立している。あるいは、完全な親の奴隷と化したマザコンになっている。 前者は高校はもちろん大学までもが、勉強のために行くところではなくなっている。果ては企業に入って自分の命が絶えるまでが一本のレールの上に乗っているのかもしれない。それは、「できる人」でも「できない人」でもないいわゆる「普通の人」である。今が楽しければ良いという楽天主義を唱える高校生は皆、「普通の人」から起こっている。自分が勉強するのではなく、まわりがするから勉強する。だから、どんなに受験方法を多様化しようが、彼らは一定の成績をあげるので実状は変化しない。根本は小中学校の教育の在り方に由来している。 後者は、幼い頃から刷り込まれた、親からの洗脳に常に従ってきた果てである。自分の考えは親の考えと同化していて、実は自分の考えだと思っているものが自分の考えではなくなっている。彼らは「できる人」に分類される。とにかく、無機的なものだけ冴えており、エリートコースを進むことになる。だが、未発達の有機的な関係が常に足を引っ張る結果になる。だから、今の教育システムで、「できる人」を優遇するとなれば、彼らを優遇するということになる。 |
7月4日
教育5.最後に
|
現今のあまりにも多い吸収しなければならない知識のために、有機的な教育のはいる隙がなかなかないのは事実である。しかし、中学校までの義務教育の中で、現在の家庭ではできない、実際の社会に即した教育、すなわち有機的な教育をする場を多段に与え、義務教育内での基本的な自立を終えたならば、この膨大な吸収しなければならない知識をより効率的に得ることができるのではないだろうか。時代が進むに連れて得られる情報量はますます増えている。たった親子間の世代の違いで、今はかなりの齟齬が生まれている。子供の教育方法の改革によって、親の意識まで変えられるような教育が求められる。 |
8月1日
批判と欲望
|
色々なものに疑問を感じては、自分なりの答えを出そうとする。"普通"の体制を批判しては、その変革を願う。しかし、今あるものを変えていこうとするときの波は強いものがあり、自分の信じる道を踏みゆくためには、相当の覚悟か動機が必要となる。 私は、この"普通"の常識とずれたベクトルに身を寄せている。身を取り巻く小さな環境が、たまたま容認するものであったのだと思う。"普通"へは、いつも近寄りがたい感情であったり、自分の中でのタブーとして働いてきた。しばらく、これで良いのだと思っていた。 だが、偶然もっと大きなスペクタクルで見得るようになったとき、大きな荒波の一波に呑まれ、とても不安定な自分を見た。社交上での"普通"にスポイルされたのだ。無意識に生まれる他人への様々な欲望が、大きな矛盾を起こしている。自分が批判をしてきたものに強い欲望を感じている。 この大きな矛盾は、自分を"普通"の感覚にさせようとしている。没個性な中に入ってしまった方がどれだけ楽になるのだろうか。 |
10月15日
埋もれる繋がり
|
誰でも、"自分"って大変です。受験生の中にいて、自分も受験生ではあるのだけれど、ぼくたちに教える人生の先輩達は、なにかと「受験勉強なんて意味がない」的な発言を繰り返します。その言葉を自分は遂行しているのか、ある問題に対して、即答えを出すという受験学力的な思考回路についていけません。自分の中の秀でる部分は、問題に対し今までの経験や勘などから、自分自身の答えを出していくうちにできあがっていくものではないのでしょうか。 そこには、ぼくが"自由"に慣れ親しめば親しむほど、度を超した享楽に自分で気づきにくくなっていくことがあります。ですがこの時代、身代わりには今の楽しみというものが最後の逃げ道であり、どうにもならないことではあるけれども、あまりにも多い抑圧対象から遠ざかりたくなるのは当然であるように思います。 自分を押し殺してまで、無根拠なことを未来のためといってやり続けるのではなく、受験学力を習得するための勉強は、"人"との繋がりの中で、今ここで彼らと関わりながら、あるいは関わるために、やっていくものだと思います。手に入れるべき能力は、独りの殻には入らずに、まわりの人達とのコミュニティーとして育むものであると思っています。 |
12月1日
男性の責任
|
男性は女性よりも「責任」を多く負うことになるのか。「責任」という言葉は身を縛る原因だ。人は一人では生きていけなく、周りの大勢の人達に囲まれてやっと生きていける。そのために、一人の人間にたくさんの「責任」が生じる。しかし、今の社会では男女の責任の差が多分にあるように思う。 産んだ子供が女の子であったから、育てるのが楽だと言う親がいる。男の子が産まれた家は大変だとも言う。女の子は将来男にもらわれていくという発想なのだろうか。男の子は将来女の子を守っていく責任があるということなのだろうか。男性は就職したときに人生の半分が決まるという。結婚したときにもう半分が決まるという。その型にはまってしまえば、あとは他人からみれば責任を果たすために動く機械に見える。きっと、人の夢というのはそういうものに押し潰されていく運命なのだ。それに、ずっと耐えてこそ大人なのだろうか。 一般的な男性にしてみれば、機械的な毎日から浮かぶ女性像というのは、毎日好きなときに寝られ、好きなときに菓子を食べられるというようにうつるのであろう。また、女性からしてみれば、出勤前の朝と疲れきった夜に毎日機械的に顔を合わすだけになっているだけの男性のことを、本当に機械に思っているのではないか。それに、主婦という立場に新しい風が吹き込むことは少ない。あまりにも波が立たない生活に憂鬱になっているようなことがあると思う。男性に対して、会社では波があるという想像のもとねたむことがあるのではないか。男女間に最低限の義務に対しての過大な権利の主張のぶつかり合いが起こりうる。波を求めてしまうのである。 女性は男性によって使われることが良くある。セクシャルハラスメントもその一つである。男性はそれによって欲望を満たすことができるが、女性からすれば、明らかに被害を受けている。しかし、注目すべき点はここで女性には二つの選択があるということである。居直ることが可能なのだ。居直ったからといって全くのマイナスということではなく、選択的にはそれで生活することも可能になっている。その点、男性は迫害を受けたときに居直ることができない。居直ったら生活がしていけなくなる。逃げてでも、自分で資金を稼がなくてはならないのだ。一般的に男性が経済的に扶養することになっていて、「経済的な」面からして女性は受け身なのである。そこに男性は「責任」を見いだす。責任は女性を養っているのだという感覚に結びつく。しかし、人間はそれだけでは生きていけないのである。身辺を管理するという生活力も必要なのだ。この二つは互いに関係しあっているが経済力の方が重要だと男性は考えてしまうのである。これを、相互不可侵の状態でおいておく先は、互いを見えなくし互いを機械だと思いこみ家庭内離婚へと続くのである。 そういう意味で男性の「責任」というのは、社会が作り上げた一方的な責任なのではないか。相互不可侵の壁を解体しようとしている社会ではあるけれども、二分された責任はいまだ権力構造によって社会的に認められることに段差がある。この段差はまた、女性が居直ることのできる特権を使うことをやめない限り残るものであるとも思う。 ***98/1/10の非公開文章を校正して社研部部誌に投稿したものです。 |
1月1日
C H I L D L I K E
始まりから自分は自分だった。 変わることのない自分は、向かい来る時間の波を裂いていく。 アイデンティティーとか価値観とか言って、他人の狭間に 「自分は?」と、骨から言えるのは幸せかもしれない。 心のハートに何本も鋭い針を刺して、血みどろにしてみても、 何故だろう、嫌ながらも供に添うCHILDがいる。 CHILDが、いつか、一緒にいける決心をしたようだ。 例えば、彼、彼女の世界を積極的に見つめるように、 世界のたくさんの夢に触れる度に洗練されていく。 大人は子供だと思う。 子供を忘れて、あるいは、変えて大人になるのではなくて、 子供をみがくことに気付くのが大人の一歩なのかなって。 いつもそばにはCHILDを。 |
連絡板へ書き込む
DIARYのindex
Mameへはmame@sun-inet.or.jp