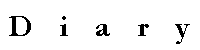
7月1日
2.個性の尊重への疑問
|
その改革のひとつである「個性の尊重」は大きな社会的不安を抱えることになるかもしれない。というのは、それが、精神が未分化な状態で教わるべき事柄ではないと思うことがひとつある。まず学ぶべきことというのは、有機的な教育の第一歩である「自己機制」だ。 精神が未分化の状態で、「個性の尊重」を教わることは、家庭外での子供のまわりにある抑圧対象を減らすことに繋がる。抑圧するものが減れば、自分のしたいことを押さえる必要もあまりなくなってくる。そして、この社会を外側から打破するならともかく(それは国の目指すところではないはず)、社会の規範に反した人材ができあがる。そのような人達は、高い自尊心故にいっそう人との繋がりを希薄にし、団結することさえできないだろう。 また、「個性の尊重」は日本が欧米型の社会を目指しているようにみえる。確かに、それは優れた人材の獲得になるかもしれないが、裏を返すと、国が必要としない低級な人をも増やすことになる。日本型社会構造の良い点は、貧富の差が激しくないところではなかろうか。それを、欧米に似せると、戦後日本では起こり得なかった、貧富の差や、犯罪の増加などが起こり得る。 義務教育期の教育は「個性の尊重」ではなく有機的な教育に焦点が置かれるべきである。そして、実践的に体感させるべきである。自分の才能がいくらあっても、今の社会のことが解っていなかったならばそれを活かすことはできない。「個性の尊重」は、高校生以降、小さなヒエラルキーの中で育んできた「生きる力」の土台の元で、はじめて自ら気づくはずである。 |
連絡板へ書き込む
DIARYのindex
Mameへはmame@sun-inet.or.jp