| NPO法人 岡崎自立生活センター ぴあはうす | 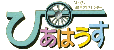 |
| Copyright (C) 2013 Piahouse. All Right Reserved. | |
| 第2回 地域を強くする |
|
「俺に言わせろ!」という挑戦的なコラムの題にして、不愉快な思いをされた方がみえるかもしれませんが、このまま行きたいと思います。 障害当事者から見た感想や地域で生きて行く意味をオレの視点で書いていき、地域で生きて行くのが当たり前だと、誰もが思ってもらえるように、そして何より障害当事者がやれる大きな役割から小さな役割までを書けたらと思っている。多くの人に読んでもらい、感想も聞けたらいいと思っている。 さて、今回は 昨年に続き、今年も岡崎市の防災訓練に参加した。 日頃からの近所づきあいが災害の時にはとても大切で、「あの家にあの人がいるぞ」と思いだしてもらうためには、やはり訓練には参加すべきだと思っていたが、何しろ私たちの地区は朝が早い。5時半集合と言うことは、1時間前には起きて準備をしなければ間に合わない。辛いなあ!と思いながらもヘルパーを依頼したら対応してもらえ、昨年の参加となった。 そして今年、近所の親しくさせて頂いている方から「災害の時なんかヘルパーさん来てくれんだら、わしが行ってやる、何でも言ってくれ」と言う言葉に甘えてお願いした。 朝5時、ピンポンと言うチャイムに慌てて起きた。寝坊をした。予定では30分前に起きて、迎えるつもりだったのに。と思いつつ近所のTさん、Sさんが部屋に入ってきた。 「すいません、寝坊しました」と言うと「しょうがないな。何からやる?」と聞かれ、シャツとズボンをはかせてもらい、車いすへの移乗を介助してもらう。 「ありがとうございました。助かりました」とお礼を言うと、「何いっとるだ、これから」と集合場所から避難所の根石小学校まで一緒に歩く。 去年は遠巻きに見ていた近所の人たちも何かしら声をかけてくれるし、福祉委員の方も去年よりも親しげな口調に変わっていた。1回の参加でこんなにも近所の人は変わってくれるのかととても安心できた。 会場では、今年から車いすの講習もやらせてもらえることになり、ぴあはうすの職員が一人、早朝出勤して行うことが出来た。 会場を回りながら、体育館では避難生活は難しいなという想いとか避難所まで来られるかという不安、トイレや寝る時は床では難しい。防災品の持ち出しの方法など実際に参加しないと気づかないことを色々と思った。 係の方から「何か気が付いたことがありますか?」と聞かれ「出入り口の靴が車いすを止めてしまった」「他の地区の障害を持った方への声かけの状況」等をお話しした。 「他の学区にもいないはずはない。参加を呼びかけようと」と言ってもらえた。 今回は、私たち夫婦二人だけだったが、来年はもっと多くの障害を持った方が参加してくれたら、防災訓練も変わるのではないかと思う。 手話通訳の活躍を避難場所の会場で見かけた。聴覚に障害を持った方の要望でつき始めている。視覚障害の方のガイドも発達障害、精神障害の方の理解ある福祉委員を育てるのも地域に住まう障害当事者の大きな役割ではないかと思う。 防災訓練に参加する障害者がいて初めて理解者が増え、地域を変えて行けると思う。日頃から近所付き合いを大切にしていきたい。 挨拶を交わしあえる地域が災害にも強い地域を作れるのではないかと強く感じた1日だった。 (この原稿はぴあはうす情報誌にも載っています) |
| 2013.10.15 |
| NPO法人 岡崎自立生活センター ぴあはうす | 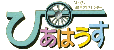 |
| Copyright (C) 2013 Piahouse. All Right Reserved. | |