| NPO法人 岡崎自立生活センター ぴあはうす | 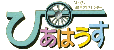 |
| Copyright (C) 2013 Piahouse. All Right Reserved. | |
| 第3回 “障害”という言葉 |
「障害」という文字が議論に上がって久しい。“障碍”、“障がい”、“しょうがい”と色々な表現があり、「障がい」というところで納まっているようで、市の福祉課も、事業の名前までもが「障がい」となってしまったが、オレは何故か納得できないでいる。そのため、ぴあはうすの書類は「障害」を貫くことにしている。 オレが思う障害者とは「障害物の多い人」という意味で、堂々と障害者と呼ばれていいのではないかと思っている。むしろそれを広めて行かないと、障害者は何時まで経っても「身体や心が不自由な、可愛そうな人」、「私は健康で良かった。大変ですね」から出られないのではないかと思っている。 多くの禁止用語がある。それはあえて書かないが、若い人たちに聞いてみると、それを知らない人も多くなった。これは文化の後退? そう思うのは、オレだけの感覚なのか? 確かに言われて気持ちのいいものではない。つい最近、酔っ払いに絡まれ、「このカタワ者」と言われ、ムッとしながらも「懐かしい! まだ使う奴がいるのか」という思いがあった。 そうなんだ! 言葉がいくら変わっても、意識の中ではまだまだ残っているというか、言葉を柔らかくして、かえって物の本質が見えなくなる可能性もある。 「可哀そうな、気の毒な人」にしているのは一体誰なのか? 今までは、障害を持った人は“障害を持ったことが不幸で、何も出来ない人”という見方で進んできたし、障害者自身も身体が動かないのは自分のせいだと思わされてきた。 時が流れ、WHOが「障害は社会が作り出したもの」という定義を出してくれた。確かに、階段は車いすでは上がれない。でもエレベータがあればみんなと同じ動きは出来る。入り口の段差、ドア、店のスペースの狭さなど・・・全てが車いすに乗っている人にとって障害となるのは仕方がない。でも、出来る限りの配慮があれば、障害は障害で無くなるのではないかと言われ始め、障害を取り除く為にバリアフリーという言葉が使われ始め、普遍化を掲げるノーマライゼーションも定着してきている。 しかし、ごく一部の人の中で動き始めているだけのことでもある。障害を持った人や家族、親戚、福祉関係者の間でだけ盛り上がっているような気さえすることがある。「大変ですね!」といった瞬間、自分には関係ないと思ってしまう。 施設から地域へと時代が動き始めている。「大変ですね!」と言っている訳には行かない時代。隣にいつ障害を持った人が引っ越してくるかわからない。みんなで地域を作り、障害のある人もない人も包みこむ地域を作らなければならない。 今までは施設の中の問題として取り扱われてきたことが、やっと社会の問題として扱われ出した今こそ、問題を出せる様な環境を作っていかなければならないような気がする。 障害者は福祉の世界だけで生きているわけではなく、様々な分野で生きている。 言葉や表現に囚われず、本質を見つめる目を養いたい。 人との会話の中で、嫌な言葉を言われたら「その言葉は使って欲しくない」と言えるような関係を作って行けることが大切だ。 |
| 2013.12.6 |
| NPO法人 岡崎自立生活センター ぴあはうす | 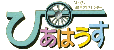 |
| Copyright (C) 2013 Piahouse. All Right Reserved. | |