| NPO法人 岡崎自立生活センター ぴあはうす | 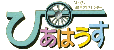 |
| Copyright (C) 2013 Piahouse. All Right Reserved. | |
| 第7回 2025年までに100万人の介護職員不足 |
厚生労働省は介護職員が2025年までに100万人が不足するという予想を受け、資格の緩和を検討することを決めた。 というニュースが流れ、初めに耳を疑った。「100万人?」べらぼうな数字だ。今でも不足しているのに、これから検討して100万人?。 10年後として年10万人が増えていかないと間に合わない。確かに大変なことになる。 ヘルパー養成講座をやっても受講する人は減少するばかり、養成講座が成立しなくなっている。そんな中、どのようにして人材を確保しようとしているのか? 予想できるのは、資格要件を下げ、報酬も下げていくというお決まりのコースが考えられる。それでなくても「賃金が低く、重労働」と言う中で、そんなことをしたら、またまた人が離れてしまうのではないかと心配になる。 今、ヘルパー募集をすると、ヘルパー2級以上か介護福祉士という資格が必要で応募が少なくなり、資格を持っている人は、在宅介護よりも条件のいい施設職員に取られてしまう。やはり条件(賃金)がいい方向に流れてしまう。 そこで、思い切った政策が必要ではないか。やる気が一番のこの仕事! 「やる気があれば誰でも介護の仕事が出来る」という条件で募集をして一定の賃金を払えるようにすれば、人は今より増えるのではないかと思う。そして3年ぐらいの期間、仕事を続けられたら、ヘルパー養成講座を今の半分くらいの時間数で受けさせ、資格を与えていく。そうすることにより人材は増えるのではないかと思う。 だいたい、養成講座を受ける人たちは障害者や高齢者を知らない人たちが多い。講義を受ける姿勢も、実際に介助どころか逢ったこともない障害者や高齢者の生活などを想像しながら理解して行くというのは非常に難しい。それよりは実際に介助をしながら分からないことを利用者さんや先輩に聞きながら覚えていく方が、はるかに理解が深まるのではないかと思う。 もう一つは、養成講座を修了しているのに現場に出ることがない人がいっぱいいる。 この人たちを現場に復活させる政策はないものかと思う。これは看護師の世界でも色々な政策が取られているが、あまりうまく行っている話を聞かない。医療の進歩や器具の取扱いが難しくなっていることが原因のようだが、介助の仕事はあまり変わってはいない。 介助に関心のある人が気軽に仕事の内容や現場を見学でき就労できるプログラム作りなどは国からの指導と予算を組めば可能ではないかと思う。 それから現役を退いた方々の活用は、どうだろう? 現在、要介護の高齢者人口が増え続ける中で、ハローワークもヘルパー養成講座の受講料を補助し、かなりの数のヘルパーを養成しているはずなのに、活躍している人の増加はあまり伝わってこない。そこで元気な高齢者を有効に活用できないだろうか? 今まで仕事をしてきた人はそれなりの技術や責任感を持っている。その資源をもう一度、介護の現場で発揮してもらえないだろうか。 アクティブは、始まって以来「同性介助」を貫いてきた。定年制も取っていない。 そしてこれからもこの方針は変えない。 私の入浴介助のヘルパーさんは74歳の男性で、とてもよい介助をしてもらっている。 時々私が「オレが生きているうちはヘルパーを続けてよ!」と言うと、「それは無理だわ!」と笑いながら答えが返ってくる。 「人の話がしっかり聞ける人、相手の状態をよく見られる人」が一番大切な資格であるような気がする。130時間も講義に費やすより、現場で叩き上げた介助者の方が利用者さんはどんなに喜ばれることか! 以前、先輩が話してくれた「福祉の制度を詳しく知っている人より、熱いラーメンを口にうまく入れてくれる介助者がいい」と言う言葉がよみがえる。 |
| 2014.11.10 |
| NPO法人 岡崎自立生活センター ぴあはうす | 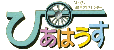 |
| Copyright (C) 2013 Piahouse. All Right Reserved. | |