| NPO法人 岡崎自立生活センター ぴあはうす | 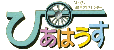 |
| Copyright (C) 2013 Piahouse. All Right Reserved. | |
| 第9回 命を預かる |
16年間飼って来たうちの黒介が車にはねられ、即死した。家の目の前の道で家の者が近所の人から教えられ、見た時にはもう息をしていなかった。 頭を曳かれたらしく、血もあまり出ておらず、苦しんだ様子もあまり見られなかった。 仕事で帰りが遅かったオレに「黒介が死んだ」と家内からの言葉に信じられなくて、段ボールに入った姿を見て、初めて実感がわいた。 いつかは来る時ではあるが、まさかこんなに突然にとは思ってもみなかった。 16年前、オレが入院中に家内が飼い出して、オレより偉そうな顔で家にいた。 「後から来た変な奴」としてオレを見続け、最後まで仲良くなれずに終わってしまった。 黒介は、オレ以外の人間には愛想が良く、ヘルパーさんたちにもずいぶん可愛がられていた。「クロちゃん」と呼ぶと必ず返事をしていたが、オレにだけはしなかった。 憎ったらしい奴であったはずなのに、なぜかとても寂しかった。 家内は16年間世話をしたという思いもあってか、権之介【初代の猫】の時ほどは泣いていないように見えた。 ケンカをして血だらけで帰って来た黒介を病院に入院させたり、鼻炎になって通院したりと色々なことがあった。黒介が恵まれていたのは近所の猫好きの方が通院ボランティアをしてくれたり、本当はいけないけれど餌をやるのをヘルパーさんが手伝ってくれたりして、黒介の愛想の良さは効果が抜群にあった。 ペットとは違うが、オレの中に凄く印象に残っている光景がある。 雨の日に名古屋からの帰り、東岡崎でどうやって帰ろうか考えている時に、ふと見ると視覚障害の方が自分はずぶ濡れになりながら階段の下で、盲導犬の体を丁寧にタオルで拭いている姿が目に入ってきた。 「これほど大事にしているのだな、自分の目の代わりになってくれる盲導犬を」と思うと同時に、自分より盲導犬を優先することに感動を覚えた。 よくよく思い返すと、いつも障害者と呼ばれる人はやってもらうことが多く、依存的になりやすい傾向にあり、美味しい所だけを持っていくというように見られがちなのだが、介助犬や盲導犬はやってもらうこともあるが、やってあげることの方が多いような気がしている。餌を与え、トイレを片付け、病気をすれば病院に連れて行く。遊び相手にもならなければならない。 命を預かっている。と感じることがある。何気なく他者のために考え、行動することは難しい。ましてや障害を持ち、親の庇護のもとで育ってしまうと、自分の要求ばかりが大きくなって、他者のことを考える余裕がなくなってしまう。 介助犬や盲導犬は物理的な自立というより精神的な自立を促しているのではないかと思う。 障害を持っている人たちが他者を思いやり、良好な人間関係を築くためにもぜひ、命を預かることを経験してみてはどうだろう。 気に入らないからスイッチを切ってしまうようなTVゲームではなく、植物や動物の世話をしてみてはどうだろうか。 葉っぱの色が悪いから肥料を与えたり、今日は暑いから水を沢山やろうとか、食欲のないペットに対して、どうしたのかなと便の様子を見たり餌を変えてみたりしながら可愛がって行く。自分も他者のために何かがやれると思える人になることは、最近特に大切な気がする。 そう言いながら、「今年はきゅうりの出来が悪い」と嘆いている今日この頃である。 |
| 2015.8.31 |
| NPO法人 岡崎自立生活センター ぴあはうす | 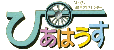 |
| Copyright (C) 2013 Piahouse. All Right Reserved. | |