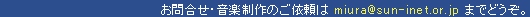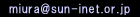私のレコードアルバム
'01/05/28
冨田勲/マイティジャック
渡辺岳夫/緊急指令10−4・10−10
スターチャイルド LP K23G-7252あれほど膨大な業績を残した渡辺岳夫だが、特撮アクション劇伴音楽が極めて少ない。「緊急指令」の他には「ザ・カゲスター」くらいである。その希少な音源が、なんと冨田勲作品と同じアルバムに収録されていたのだ。ミウラが最も愛する二大巨匠、夢の共演である。今、新たなる感動とともにこの盤を紹介できることを誇りに思う。(おおげさ)
実はこのLP盤、つい最近ネットオークションで落札したもの。現在では、このLPに収録された楽曲は、VAPの偉大なる「ミュージックファイルシリーズ」のCDで聴くことができる。にも関わらず定価の数倍で落札したのは・・・。白状しよう。コレクター的な感覚である。それを(ジャケやおまけポスターも含めて)自分のものにしたいという単純な欲望であった。硬派を気取っていますが、たまにはそうゆうこともあります。
マイティジャック
今更何も申し述べる必要は無い。日本が誇る特撮ドラマの金字塔である。これに対抗できるのは同じ円谷プロの「ウルトラセブン」くらいだろう。「マイティジャック」は変身ヒーローが出てこない、大人向けドラマとして製作されたのだ。しかも日本初の一千万円ドラマで、なんと放映は夜8時からの一時間枠であった。この番組を知らなかった人がもしもいたら、一日も早く鑑賞するように。'68年作品である。
緊急指令10−4・10−10
こちらは若干シブいこちらは30分枠の番組だ。知らなかったからといって叱りつけるわけにもいかないだろう。変身ヒーローが登場しないのは「マイティジャック」と共通しているが、主人公である電波特捜隊の青年達は市民無線で連絡を取り合って活動する。市民派な連中だ。当時はもちろん携帯電話なんか無かったのだ。'72年作品である。
'98/05/30
三原順(原作)
谷山浩子(音楽プロデュース、作詞、作曲、ナレーション)
山川恵津子(編曲、シンセサイザー)
CANYON C25G0164A面
「われらはみだしっ子」(全員の歌)
「笑い猫」(アンジーの歌:藤田淑子)
「ボクは鳥だ」(サーニンの歌:間嶋里美)
「冬の果実」(グレアムの歌:小山菜美)
「Smile for Me」(マックスの歌:雪野ゆき)三原順の同名コミックをベースにしたイメージアルバムです。谷山浩子の音楽プロデュースでナレーションもしますが、彼女の歌は無しです。難波弘之がピアノで参加しています。
アンジーの歌は斜めに構えたような個性を反映し、翳りがあってナイス。A面全体では、後半の曲ほど好きになりました。ただし各キャラの歌をそれぞれの配役の声優さんが歌っており、曲の良さと歌の上手さ加減が必ずしも一致していません。谷山さんの歌も聴きたかったな。
B面はドラマと音楽です。B面の音楽はインストものです。ドラマ部分にも音楽があって、谷山浩子&山川恵津子によるサントラのようにも聞こえます。ドラマ編の「だから旗ふるの」は、原作でも印象深いエピソードなのだ。
'97/10/04
玉木宏樹/シンセサイザー交響曲「雲井時鳥国」
玉木宏樹、大原繁仁、乾裕樹、安西史孝、松武秀樹(シンセサイザー)
尾高忠明指揮
東京フィルハーモニー交響楽団
CBSソニー LP 28AG417「シンセサイザー協奏曲」ではなく「シンセサイザー交響曲」としたところにこだわりがある。レコーディングは大規模で、オケ用マイク36本、シンセ関係12ラインの合計48入力を24chレコーダーに録音した。マスターテープは1/2インチ幅を76cm/sで使用。シブイチのツートラサンパチ(1/4インチ幅で2トラック38cm/s)の四倍である。さらに、このレコード自体はLP版なのに45回転なのだ。横尾忠則のジャケット画がカッコ良い。
第1楽章「雲」
重苦しい雰囲気から、やがて嵐になります。この始まりかたは「新世界」のようだ。「新世界」も「雲井時鳥国」も第一楽章が最もドラマティックであると感じる。第2楽章「時」
この第2楽章をFM放送で聴いたのが、アルバム購入のキッカケであった。本人は「シッチャカメッチャカな展開」と表現されていますが、存分な爽快感であります。第3楽章「鳥」
個人的には一番気に入っている、おだやかな楽章。この第3楽章では、ローランドのボコーダープラスVP330が活躍する。第4楽章「国」
終楽章にふさわしく「それではみなさんごきげんよう。」という趣。「国」は、メロディー的には一番聴きやすい。
'97/07/20
ヴィヴァルディ/合奏協奏曲「四季」
フランク・ベッカー(シンセサイザー)
辰巳昭子(ヴァイオリン)
東芝EMI LP TA-72041今回で紹介するアルバムは比較的地味な一枚。シンセ音色はアナログ的なストリングス系が中心である。さらに特徴的なことには、ヴァイオリン・ソロだけがシンセではなく本物ヴァイオリンの演奏であること。ヴァイオリン協奏曲なのだから、独奏ヴァイオリンだけは「聖域」として、手を加えなかったのだそうです。そのくせ「楽譜の書き込みから想像した」SEを混ぜてある。こんな演奏に何の意味があるのか?。などと問うことなかれ。シンセ黎明期にはいろいろあったのだ。
「四季」の場合はメロディーがはっきりしているので、シンセ使用以前にもアレンジものがあったわけです。故にシンセ版は、「新たな試み」というよりは、商業クサい感じが・・・。帯には「ヴィヴァルディ生誕300年記念」なんて書いてあるぞ。
'97/07/13
「シャイニング」オリジナル・サウンドトラック
メイン・タイトル〜ベルリオーズ/断頭台への行進
ロッキー山脈
ウェンディ・カーロス(シンセサイザー)リゲティ/ロンターノ
バルトーク/弦楽器と打楽器、チェレスタのための音楽
ペンデレツキ/ウトレンニャ、ヤコブの目覚め他
演奏:カラヤン、ペンデレツキ他
WP LP P-10894Wこのころはすでに性転換を終えて、ウェンディを名乗っている。残念ながら、カーロスの音楽はたった2曲収録されてるだけです。その他は聞いたこともないような現代音楽ばかり。いわば従来のクーブリックにもどったといえる。今思えば、こんなサントラどうして買ったのかしらん?。ようするにイキオイで買ったのですね。クーブリック&カーロスならなんでもOkだったのです。ところが、アルバム自体は全然わけがわからん。それも2001年くらいならなんとかついていけても、一度にこんなにいっぱい提示されてはカナワン・・・というわけで保存盤(保存するだけ)になった一枚です。
一本の映画サントラのために、自分の音楽領域を律儀にひろげていたら大変です。
今、このアルバムをあらためて手にとって見ると、オヤぁバルトークの「弦打チェレ」が収録されておられる。
あれまぁ。でも悪いのはこのサントラアルバムです。日本語による作曲者名の表記がないのです。現代音楽なんて、最初っから聴いてもらおうなんて気持ちはなかったのだろうね。このアルバムが発売された当初から愛聴盤だったという強者はおられますか?。
'97/07/06
「時計じかけのオレンジ」オリジナル・サウンドトラック
パーセル/クイーン・メリー葬送曲
ベートーヴェン/交響曲第9番「合唱」第2,4楽章
ロッシーニ/「ウィリアムテル」序曲
カーロス/ベートヴィアーナ、タイムステップス
ワルター・カーロス(シンセサイザー)
他に原曲版を収録
WP LP P-6352W「スイッチト・オン・ベートーベン」
カーロス/いなか路、ベートヴィアーナ、タイムステップス
ベートーヴェン/交響曲第9番「合唱」第2,4楽章
パーセル/クイーン・メリー葬送曲
ロッシーニ/「どろぼうかささぎ」序曲、「ウィリアムテル」序曲
ワルター・カーロス(シンセサイザー)
CBSソニー LP SOCL 202スタンリー・クーブリック監督の映画「時計じかけのオレンジ」オリジナル・サウンドトラック盤である。クーブリック監督は、もともとクラシック音楽を劇伴に使用しているので、カーロスの起用は自然な流れか。カーロスのオリジナルアルバム「スイッチト・オン・ベートーヴェン」と「時計じかけ」サントラは、収録曲目がかなりダブッております。ファンなら両方持っているよね。
YMOやカーロスを夢中で聴いた高校生のころ、モノフォニック・シンセでさえとても買えない高嶺の花でした。同級生がYAMAHAのCS-10を買ったのがうらやましかったです。これはキーボードのくせに和音が出ないシンセなんだね。
'97/07/04
「スイッチト・オン・バッハ」第1,2集
J・S・バッハ/ブランデルブルク協奏曲第3,5番、管弦楽組曲より「バディネリ、メヌエット、ブーレ、アリア」、二声のインヴェンションより、カンタータ「羊は安らかに草を喰み、主よ人の望の喜びを」、他
ワルター・カーロス(シンセサイザー)
CBSソニー LP 23AC 530,571「スイッチト・オン・ボレロ」
ラヴェル/ボレロ
シャブリエ/エスパーニャ
「カルメン」より第1幕への前奏曲、ハバネラ/ビゼー
ワルター・カーロス(シンセサイザー)
CBSソニー LP 23AC 551あのカーロスです。「もうでてくるころだろう」と期待していたみなさん。お待たせしました。案の定というか、やっぱり登場しました。
3枚とも、CBSソニーの堂々たる「ニュー・ベスト・クラシック150選」である。
モーグ・シンセサイザーによる「スイッチト・オン・バッハ」で大ブレイクしたワルター・カーロス。その後性転換してウェンディ・カーロスを名乗っている。シンセサイザー自体もその後進歩しまくって、今時「シンセ」なんて言葉を使う人も少ないくらいである。このアルバムも今聴くと安っぽい音である。「こんなんでブレイクできるなら、俺だってもうウン十年早く生まれていれば・・」と誰もが思う。
でもそこは音楽なんだから、最初にやったもん勝ち・・だけじゃぁありません。「スイッチト・オン・ボレロ」は小粋でオシャレな演奏です。機会があったら聴いてみよう。何をかくそう、有名なバッハのメロディーのほとんどを、ミウラはこのアルバムで覚えました。その後バッハのオリジナルや、バッハのその他のアレンジものにも親しみました。わざわざ親しまなくてもよさそーなものですが・・。
'97/06/29
ホルスト/組曲「惑星」
リチャード・R・ベネット
スーザン・ブラッドショー(ピアノ)
FACET 8002みんな編曲したくなるのに「編曲は禁止ぢゃ!」と遺言された。編曲版のほうが有名になっちゃうことを恐れたわけでもないでしょうけど・・。ミウラは高校生のときに吹奏楽版を演奏したことがある。ホルスト自身が吹奏楽曲を多く残しているけど、吹奏楽版は本人または遺族公認なんだろうか。
ここで紹介するアルバムは二台ピアノ版である。「またまた妙なアレンジものか」とあきれなくともよろしい。これはホルスト本人の作である。「といっても、しょせんオリジナル管弦楽版とはくらぶべくもない」などとほざかないこと。こっちのほうが先にできたんだから・・。

'97/06/27
ムソルグスキー〜ストコフスキー編/
組曲「展覧会の絵」
ドビュッシー〜ストコフスキー編/「沈める寺」
レオポルド・ストコフスキー指揮
ニュー・フィルハーモニア管弦楽団
キング・レコード K15C 8024「展覧会の絵」にはいわずとしれたトミタ版や吹奏楽版もあるけど、もっとも有名なのはラヴェル版で、これを原曲だと思っている人もいる。その人物がピアノ版原曲を聴いて「やはりオリジナル管弦楽版にはかなわぬのだ」・・おいおい。
ストコフスキー版の特徴は「チェイルリーの庭」と「リモージュの市場」が無いこと、プロムナードが3回しかないこと。原曲は5回、ラヴェル版は4回。「沈める寺」の原曲もピアノ版で「前奏曲集」の1曲。豊かな色彩感もさることながら、そのサウンドは今聴いても迫力がある。
ストコフスキーは英国生まれで、米国で95才まで活躍しました。吉本調の映画「オーケストラの少女」には、本人役で出演してるので観てみよう。
このレコードは PHASE 4 STEREO である。その昔に4チャンネルステレオが流行したが、方式の乱立で全滅した。最高の音質を誇るFFSS録音であり、これは全可聴周波数帯域ステレオ・サウンド意味する。

'97/06/27
ヴィヴァルディ/合奏協奏曲「四季」
ギュンター・ノリス・トリオ
ギュンター・ノリス(ピアノ・チェンバロ・オルガン)
チャーリー・アントリーニ(ドラムス)
ジャン・ウォーランド(ベース)
東芝EMI EAC-80215ベートーベンの合唱とともに、日本にはなくてはならぬクラシック曲(なんで?)である。おそらく四季というタイトルのせいだろう。ヴィヴァルディの評価は20世紀になってから高まったそうだ。
四季のアレンジモノはいろいろあるけど、ギュンター・ノリスは、ジャズ版である。トリオとはいいながら、ノリスはマルチ録音でピアノやチェンバロを弾きわけている。ひとりでチェイス(かけあい)などやってのけるのが面白い。演奏はやたらと親しみやすく、ジャズというよりは、トリオスタイルのイージーリスニングといった趣。
おやぁ、我が家のキーワード(青字)が全部登場しましたね。
このアルバムにはトゥールーズ室内管弦楽団の演奏も収録されている。西ドイツ本国では、それぞれのアルバムとして発売されたが、日本では1枚で両方聴けてしまうお徳用。
四季のアレンジ演奏にはいろいろあって、このほかにも畑野亨のキラキラサウンドの四季も聴きました。キレイでした。

'97/06/27
豊田貴志/「彗星」
豊田貴志(シンセサイザー・ピアノ・ヴァイオリン・Eギター・ベース・コーラス)
畑野亨(ドラムス)
CBSソニー 27AH 1111豊田貴志。このミュージシャンについては、このアルバムの解説に書いてある1980年までのプロフィール以外ほとんど知りません。何の予備知識もないままレコード店で買ったものが、すごく気に入っています。クラシック音楽と直接的なつながりはないが、あえて紹介します。サーチエンジンで調べたら、豊田貴志は新潟県の黒川村胎内平での第14回胎内星まつりで演奏とあった。
太陽系をめぐる彗星をテーマに、地球・火星・木星などのシンセサウンド絵巻といった趣である。当時のトミタばりの迫力があるが、アレンジはメロディアスで聴きやすい。本人のヴァイオリン演奏までミックスされており、実に美しい響きをもっている。
明らかにホルスト〜トミタ惑星を意識している。はっきり言って亜流だけど、タケノコみたいに言うのは、はばかられる。軟弱なプログレ風でもある。でも好きになっちまったものはしょーがない。