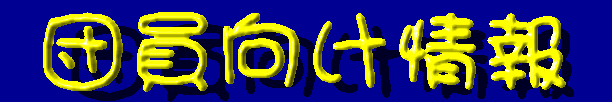
更新日 2002.11.13
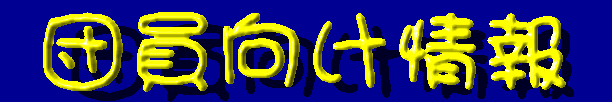
お客様への「第九」の案内状でバリトン歌手を紹介されていた先週号のつづきのようなものです。
もちろんわたしもパク・ウン・ウー先生を存じあげません。とても楽しみにしています。20年前に商社マンとして3年半駐在した思い出深いソウルからやってこられる方ですからお待ちする気持ちがひとしおなのです。
当時はいまとちがってなにかと物情騒然としたソウルの街でした。午後5時に市役所など公共施設の屋上に揚げられいる国旗がおろされるときスピーカーで流される国歌は、地上のどこを歩いていても立ち止まって旗を見上げ、直立して聴かなければなりませんでした。さすがにいまはやっていないようです。
現地社員からの賃金交渉(猛烈な)をはじめややこしい仕事のかたわらできるだけ現地の文化に触れるようにしました。古典芸能の催しにもよく足を運んだものです。日本の浪曲のような節つきの語り(パンソリ)を、しぐさと節回しがおもしろくてストーリーをまったく理解できないまま3時間聴いていたことがあります。クラシックの演奏会も出来るだけ行くようにしていました。日本のN響に相当するKBS交響楽団の定演や東京フィルハーモニー交響楽団の来韓公演を世宗文化会館で聴いたりしました。プログラムがはじまる前にはチェロ以外の演奏者が全員立ち上がって国歌が演奏されます。聴衆ももちろん座席で起立して聴きます。日本のオーケストラの場合は日韓双方の国歌が演奏されることもちろんです。いまはどうなのか知りません。パク先生はお国だけでなく世界的に活躍されているようです。どんなバリトンを聴かせていただけるのでしょうか。もうすぐですね。
なお、蛇足ながら、当時はたどたどしくしゃべっていた韓国語はその後使う機会がなく、さらに急激な老化も手伝っていまや遠く記憶のかなたに消えてしまい、まるきり通用しなくなってしまいました。 (BUS)
秋、高い空、いかがお過ごしでしょうか。
今年も第9のご案内をお送りする季節となりました。
今年の目玉はバリトンのソリスト。韓国から、パク・ウン・ウ(朴興雨)氏をおねがいしました。
日本の年末、山程のさまざまな第9があふれ。”一万人”のような『みんなで参加、お祭り型第9』もあれば、古楽器など用い『当時の姿追求型』もあったり。ではフロイデは、というと、40年以上にわたって『ベートーヴェンが第9にこめたメッセージをとことん追求』しております。「ベートーヴェンがこの詩を音楽で伝える上で、どんな声、響きがふさわしいと思っただろうか」を、ああでもない、こうでもない、と、毎日、毎日、考えつづけ、それが合唱団の響きづくり、オーケストラの音づくりにつながります。もちろんソリストも、例えば”ソプラノ”も”こういうソプラノの声が欲しい”ということで決定されます。
さて、バリトンソロですが、ご存じのように第9のバリトンは、第1~3楽章の音楽の後、人間の声としての第1声「おお、友よ、この調べではない!」を発する重要な役割り。ことばにふさわしい響きの持ち主が欲しい。…と、ずっと探し続けてきた外山雄三先生が、今年、仕事で訪れた韓国でその声を聴いたとたん、「この声以外にない!」とほれ込んだ。そのバリトンがパク・ウン・ウ氏でした。さて、その響きの程は!?
私たち合唱団もベートーヴェンの心を深く豊にお届けできるよう練習練習練習…です。
12月8日、お忙しいことは存じますが、ご都合よろしければ、お聴きいただけましたら、幸せに存じます。 (is)
先週は、今回初めての外山先生の練習でした。私は、第九で外山先生がおいでになる頃になると「あ、本番が近づいてきたな」と気持ちが引き締まります。そして、演奏会までにクリアしなければならないことの多さに一瞬ぼう然ともするのです。
練習ではたくさんの指摘がありました(雑の練習メモにもう一度目を通してください)。それはべートーヴェンが第九に込めた「自由・平等・連帯」という精神をお客様に伝えるための方法としての技術であり、フロイデの第九を歌うためには必ず実践しなければならないことです。普段の練習での指摘も合わせて体に覚えさせること、これが私たちの“暗譜"なのですが、言うのはたやすく、それが如何に難事であるかは回数を重ねるほどにいやというほどわかってくる…
私たちアマチュアの練習というのは、少しでも気を緩めると鼻歌のごとく楽に歌っていることに気づき、これではいけない、と思い直しても、また・・ということを繰り返しながら身についていくのでしょうが、その道のりは遠い。一年や二年でとても歌えるものではありません。フロイデ合唱団が40年間歌い続けても、もちろん毎年新しいことに挑戦しているからでもありますが、これだけやっておけばいいのだというマニュアルなど決してない「第九」とはなんという恐い曲なのでしょう。
演奏会を成功させるためには「演奏と財政」という条件が不可欠ですが、あまたある課題の一つひとつを、今何をすべきなのか、と考える不断の努力によって乗り越えながら、演奏会に向けて気持ちを高めて行きたいものです。 (B.Go)
○過日、NHKTVで群馬交響楽団の第九の取リ組みを放映していました。ご覧になったかたも多いと思いますが……様々な場面で、ご苦労のほどがしのぱれました。
苦労といえば、今まさに苦労の真っ只中に、団員のみなさんの殆んどがあるといえましょう。新入団貝のかたも、苦節十数年のベテランも、あらたな発見をしながらもがき、苦しんでいるといえば、言い過ぎでしょうか?!……「響かせる」にはどうしたらいいのか、ムンクの叫びスタイルの発声法もひとつのやリ方、あなた自身それをいま体感しておられるはず!要は本番で練習時の力が発揮できるかな?ですが……。特効藁はあリません、あたりまえのことですが地道にやるしかないのです。先生の指摘をカラダで受けとめて「響き」を常に意識しましょう。
○数年前のこと、仕事の都合で金沢近郊に住んでいたことがあります。この街に「オーケストラアンサンブル金沢」という楽団があることはご存釦だ思いますが。その『響き』のよさはつとに知れわたっていて、切符が即売り切れてしまうほどの人気!在金中に何度か石川音楽堂へ足を運び聴かせて頂きましたが、岩城宏之さんの棒で紡ぎだされる「響き」……昔だけでなく心への「響き」に感銘をうけたのを思い出します。私達フロイデもO・E・金沢に勝るとも劣らないほどの気合いをもって望みたいものです。、
○先週港区で開かれたインターナショナルオーディオショーを観に(聴きに)行ってきました。各国の技術の粋をあつめた大がかリのものでしたが…すごいと感じたのはドイツのA杜が出品したスピーカー、お値段も一戸の家が買えるくらいの「超」価格、それはさておき、「響き」!「圧倒的な音量、響きと質感……ただ感嘆するほかありませんでした、まさに筆舌に尽くし難い!とはこのことと思った次第。
○「響き」…単純に音の響きだけでなく、心の「響き」も伝えられるよう、練習に集中していきましょう。 Bass yo
‥‥‥‥会場の仮予約は1年前から‥‥‥
最近、舞洲の野外活動センターでやることが多いのですが、ここも公共の施設なので早い者勝ちではなく、もし、今週はムリです~なんて事になると、他の会場を探さなければならない。なので、本予約と決定されるまで、実は、ちょっとドキドキ!!普段の練習会場取りでも、そうなのだろうけれど。
‥‥‥‥2ヶ月前から申し受け付けの準備開始‥‥‥‥
「合宿のしおり」と申込用紙の作成-印刷大臣に原稿を渡しておくと、翌週、配布物の机に並んでいます。申込期間を決めて、受付嬢さんに連絡-練習会場で、いつも受付の席に座ってくれています。
10日程前に、ロッジ舞洲へ参加人数、弁当の数、宿泊の部屋割り等の連絡を入れます。あと、バス増便の手配、懇親会の準備などなど、合宿前の1、2週間って、私のちょっと落ち着かない日々なのだ~!!
‥‥‥‥当日‥‥‥は意外とやることがない。
というのは、まわりの皆がいろいろ動いて下さるので。私はお金を持って、あっちへウロウロ、こっちへフラフラしているだけやなあ‥‥。
事故の無いように、じゅうじつした2日間を過ごしてもらえるように、ただ気を揉んで♪
そうそう!いちばん気になるのはお天気です。特に日曜日は、外で弁当を食べたいし♪
‥‥‥‥後日‥‥‥‥
収支報告をして、会計さんに申し込みの残金を渡して無事終了~♪
また、次回も頑張るぞっと!!
私が子供の頃、親戚のおじさんが「第九はいいぞ、お前も大きくなったら一緒に第九をやろう。とよく言っていました。幼心に「大工さんってそんなにいい仕事なんだ。僕も頑張って大工さんになるぞ。」と心に誓いました。
つまらんギャグで始まってすみません。それでもって大きくなって子供の頃誓ったように第九を歌っています。でも第九って難しいですね。何回歌っても難解な所が泉のように湧出てきます。特にフロイデの第九は毎年歌い方が微妙に違うから始末に負えない。3年半ぶりに帰ってきたら完全に浦島太郎状態。昔のように歌ったら怒られるし、歌わないで小休止していたら。何と先生「今のテノールは良かった。」だって。もう最初のうちは完全にパニック状態。開き直ってでかい声出したらまたまた・・・。科学もフロイデも年々進化しているのでありました。そういえば3年半前は写メールなんて無かったもんなぁ。
パニクっているうちに後1ヶ月で本番「ああどないしょう。ちゃんと歌えるんかいな。「一人だけ2回目のalle Menchenのとこで飛び出してしまうんとチャウか。」「男声合唱で間違ってソロを歌ってしまうかも」等等心配し始めるときりがない。結局一生懸命練習して自信をつけるしかないのであります。なんてったってお金を頂いて歌うんだから。料金を頂いてのコンサートですから本番時にはプロの意識を持ってステージに立たなければならない。タダなら少々出来が悪くってもお客さんは勘弁してくれるかもしれませんが(失笑や途中退場はあります)、5千円近く取っていたら失笑どころではない「金と時間を返せ」であります。
2千数百人聴衆の大半に「次のコンサートにも是非来たい」と思わせる演奏をしたいし、皆で頑張れば出来る(かもしれない)と思っています。必ず出来ると信じて練習しましょう。最高のステージが終わった後のビールは最高に美味い。今から楽しみです。
なんだか団長やパートリーダーの檄文みたいになつちまいましたが、別に後釜を狙つているわけではありませんので誤解のないよう。
追伸 テノールはあんまり頑張り過ぎないで。息を沢山使ってファルセット気味に。
15年振りの第九に臨んで夜空のもと家路につくとき、よくこの時が与えられたと思う。いずみホールからの帰り、フロイデ合唱団のパンフレットを渡されなかったら、又、そのパンフレットを大事に持っていなかったら、「第九」と「モーツアルトのレクイエム」のCDをたまたま7月20日に買わなかったら、この日はなかった。なんとも不思議なめぐり合わせに感謝。
「合宿」という響きに哀愁を感じながら参加した合宿。精一杯声を出して疲れて帰宅したはずなのに、なぜか心は充実していた。先輩たちの発音にはまだまだ届かない己を知る。この合唱団に加えてもらい、亀井先生をはじめとした、諸先生方の指導を受けられることを本当に嬉しく思っている。
練習日も本番に向け半分を切った。みんなで声を合わせて心を合わせて歌おう!! FREUDE♪ と
グループ名鑑では、何時も団歴を書く事になっておりますが、毎回、「入団1980年、しかし歌うこと7年+3年目」と訳の判らない団歴を書いております。 これは、1988年から、15年間サボッていたと言う事でして、その間の殆どは田舎に単身赴任しておリました。4年ほど前に帰阪、地下鉄御堂筋線で、たまたま練習帰りで酔っ払いの岩井さんに遭遇、団に復帰したと言う次第です。現在は、練習にはかなりの高い参加率を持っており(ドイツレクイエムは100%)、大阪在住を証明しております。しかし、しかしですよ、これは、フロイデにおける話。業務上、出張で早発ちや泊まりが多く、また、仕事でも練習でも遊びでも、出かけたら帰宅は夜中。家庭では、父親の存在に気が付くのは『夜中の大いびき』だけで、息子に言わせると、「単身赴任の時と変わらない。」そんな生活の中で、自慢できる事は、スケジュールを組む時、【練習日は、出張しない、接待しない、仕事をしない】をモットーにしている事です。最も、合唱団以外では、「ばかちゃうか!」と言われる様な話ですけど。 B.ヒゲ
日本初演から50年を記念して、9月20日に「森の歌」が演奏された。
(桜井先生指揮、テノール、バス、混声合唱、児置合唱、大阪シンフォニカ)
初演の翌1954年夏、労音合唱団の一員として3ステージに立ち、学校・職場を通じての合唱経験のなかで味わった事のなかった大合唱の素晴らしさに開眼した私を、その後の労音活動へと導く大きな意味を持つ曲である。
桜井先生が「少々否定的な問いかけ『今なぜ森の歌か』という問いに対する答えになってほしい」とおっしゃっているがほんとうにその通り聴く人は必ずこの曲の理想は現代においてこそ尊重されるべきものと納得するだろう。
第1章でバスと男声合唱でうたわれる喜び、その伸びやかなメロディ!『歌は地に満ちて花火空を飾る』私は聴きつつ心中で唱和していた。3柏子と4拍子が交代したり、4分の7拍子など歌った事もなかったフーガ等々、又アルトといえど高音が要求され、詩も日本語訳であるからこそ内容をよくつかんで・・・万事難しい練習だった。
けれど敗戦にうちひしがれながらも新しい日本、新しい世界を目ざして若い私達はひたむきに生きていた。その私達にこの曲は緑の帯を地球に広げよう、荒れた地に豊かな水を、と呼びかけているのだ。何という希望だろう。人の力だけでなく大きな自然の命との共存をたたえているのだ。
山を崩し、森を倒し、そこに住む人を追いやってダムや道路を造ろうとする現在の日本の在り方と正反対の考えを持つ人々も多い筈。児童合唱がうたうように『ぐみもりんごもポプラを皆々育ちゆけよ。野に満ちて!』そして子ども達こそ豊かな緑に囲まれて伸び伸び育ちゆけよ、と歌いたい。
1973年にこのフロイデで私は歌ったのであるが、今もってフロイデに在籍し続けたい思いの根っ子には『森の歌』が与えてくれたものの力があるのかもしれない。 A 美穂
この時期なのにみなさん細かいところまでよく気をつかってやってくれている。当然、この曲が持っている難しさを越えるところまではとどいていない。それは、一人ひとりが、その難しさを気にして練習することです。第九は、ベートーヴェンの音楽はどのパートもとんでもなく難しい。そのパートの音域をはるかに超えた高音が続いたかと思うといきなり低くなったりする。これは作品の持ってる難しさです。
ベートーヴェンは人が楽しむことを許さない。(ブラームスは、ああきれいだなぁ、というところはあっても)ベートーヴェンは気がぬけない。聞く側も本当は「よし聴くぞ」と気合いを入れてないとわからないところがあるのかもしれない。世の中には、第九はたくさん演奏があって、それはいろいろあっていい。しかし、大阪のフロイデ合唱団と大阪フィルハーモニーでフェスティバルホールでの第九は、私たちが本当にやりたい第九ができるところだと感じている。新しい人をいっぱい加えながらでも合唱団の性格というのが必ずあって、信頼関係がある。みなさん、お一人おひとりが、私は第九をこう思う、を出して下さって、それをまとめるのが指揮者の役割だ。
第九の難しさを越えるために一人ひとり工夫どころがちがうはずだ。一人ひとりが工夫して下さい。






