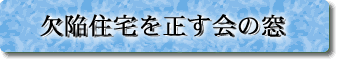|
|||
昭和53年以来24年に亘って欠陥住宅被害者救済活動を続けている
|
|||
| -正す会の窓・・・その15(論説)- | |||
欠陥があった場合消費者は業者に |
|||
|
|||
1 瑕疵担保責任の意味――自己補修との違い(責任としての補修) |
|||
買ったり注文したりした建物に雨漏りや結露、傾きといった欠陥があった場合、消費者は業者に対してどのような請求ができるでしょうか。 「修繕をしてもらえる、手直しをしてもらえる」というのが普通の考え方でしょう。 それを法律では「瑕疵担保責任」という難しい用語で呼びます。 「 瑕疵 」とは、もともと「瑕」も「疵」も「玉にきず」のきずで、「よいものの中にまじっている悪い点」という意味です。 この言葉は、明治 32 年につくられた今の民法の中に出てくるもので、当時の立法者の念頭に、現在皆様方を悩ましている手抜き欠陥というようなものは全くなかったものと思われます。 というのも、農村でも都会でもお互いに顔見知りの共同社会を基本に、その社会の中に住んでいる大工や棟梁に建築を依頼するというのが当時の住宅の生産システムだったからです。 また、建物自体も田の字型の極めて単純な木造住宅だった上に、地域の一般の人々もその棟上げに参加したり、子供たちもその建築現場で遊ぶなどして、家のつくり方に関してある程度の知識を持っていました。また、建築に限らず、当時はどのような職業でも職業倫理が貫徹しており、金もうけのためにするというよりは、自分の道として、自分の仕事として、自分のあり方として、自分の人生として仕事をしているという色合いが強かったため、現今横行している手抜きのようなものは当時の職人社会では全く予想もされなかったのでした。 このようなわけで、民法制定当時の日本社会では、今横行している故意に材料や手間を端折るといういわゆる手抜きは見当たらず、また建築関係者の間でもそのようなことは埒外のこととして話題にも上らなかったのです。 そのため明治時代の立法者が考えていた「瑕疵」は、確かに家の欠点ではあるけれども、故意に材料や手間を手抜きしたことによる欠陥ではなく、例えば大工が誤って床柱を傷つけたというようなまさしく「玉にきず」の「傷」のことで、人間である以上だれでも起こし得るミスという色合いが強く、上手・下手という言葉と連続性を持っていました。 そこで、「補修費用に過分の金がかかるような少々の欠陥は補修しなくてもよい(民法 634 条)」とか、「たとえ契約の目的を達しなくてもでき上がった家の契約解除はできない(民法 635 条)」という請負人保護の民法の規定が生まれたものと考えられます。 瑕疵担保責任とはそのような背景をもとに生まれたもので、「瑕疵担保責任」を文字どおり読めば、まるで欠陥をつくるのを担保する責任のように聞こえますが、実は「瑕疵がないことを約束する、担保する責任」という意味で、欠陥があればそれをまず補修して約束した設計図書どおりの状態にするとか、設計施工で設計に欠陥があれば、その設計自体も改め、その分についての施工もし直すということが本当の意味なのです。 また、法律では、 欠陥の補修にかえて、 または 欠陥の補修とともに損害賠償を請求する ことができるとしています。 一たん欠陥がつくられると欠陥をつくった人に対する当然信頼は薄れますし、また美匠や仕上げの欠陥などのように補修をすればするほど家が損じるという場合もあります。 そこで法律では、消費者に対して現実の補修を求めてもよいし、現実の補修にかえて補修相当の代金と、欠陥によって附随的に発生した損害をも請求できるとしています。 この場合の 欠陥によって附随的に発生した損害 とは、欠陥原因をはっきりさせるために建築士に依頼し、相当な補修方法の教示を受けた費用などのことです。ですから、欠陥があった場合には、一次的には補修の請求をすることができ、それにかえて相当な補修代金を請求することもできれば、あわせて欠陥によって生じたさまざまな諸費用や損害などをも請求することができるというのがこの瑕疵担保責任という法律の用語の意味です。 ここで間違ってはならないのは、瑕疵担保責任による補修請求は、所有者が古くなった自己所有の建物のメンテをするなどの自己費用による補修( 自己補修 )とは違うということです。 あくまでも法律に基づく 責任としての補修 であって、原則は契約で約束された状態、つまり設計図書どおりの内容に建物をし直すという意味です。 なお、瑕疵担保責任の内容として述べたのは請負に基づく場合のことで、 売買の場合 は一次的には瑕疵の補修を求めることはできず、 契約の解除と損害賠償 が瑕疵担保責任の内容となっています。 また、単なる欠陥ではなく、 隠れたる瑕疵 (引き渡しを受けたときには消費者にはわからなかった欠陥)を対象としています。 しかし、現今横行する手抜き欠陥の大半は隠れたる瑕疵に当たり、請負とさほどの違いはないものと思われます。 また、現在では売買によるときでも補修を求めることも慣行的に認められています。 尚、品確法では売買のときでも新築建物については補修請求を認めました。 |
|||
2 瑕疵担保責任又はそれ相当の賠償責任はだれに求められるか。 |
|||
請負でも売買でも契約上の責任となりますので、 契約をした請負人 なり 売り主 なりにその責任の履行を求められるのは当然のことです。 しかし、このごろの判例の進展で、欠陥が設計者の設計に起因する場合には 設計者 に対して、工事監理者として選んだ建築士が適切な管理をせず、例えばさぼっていたために施工関係者が手抜きした場合にはその 工事監理者 にも損害賠償責任を求めることができるようになっています。 ただし、設計者や工事監理者など契約当事者以外の第三者に業者と同じ責任を求める場合には、法律上は瑕疵担保責任ではなく損害賠償責任となり、法律の適用条項も、瑕疵担保責任が民法 634 条であるのに対して、損害賠償責任は民法 709 条の不法行為責任として請求することになり、この場合には 不法行為責任 と呼ばれることになります(契約上は第三者のため)。 同様に、 仲介業者 に責任を求められる場合もあります。 最近よく問題になっているのは地盤の瑕疵で、工場跡地で工業廃棄物などの人体に悪影響を及ぼす公害物質が地中に含まれているのを仲介業者も知っていたのにそのことを黙っていたという場合、仲介業者であっても責任を問われることがあります。 この場合は不動産売買の仲介者としての責任で、消費者との間には仲介契約という直接の契約関係がありますので民法 415 条の契約上の 債務不履行責任 となりますが、これも不法行為責任と同様、瑕疵担保責任とそれほど内容的に違いがあるものではありません。 また、構造に関する手抜きで、設計図書で要求されている柱や梁の配筋を故意に落とした場合には、他人対し危害が及ぶのを認容していたものとしてその工事を担当した 施工責任者 や 主任技術者 (建設業法上、現場の管理をする責任者)の責任を求めることもできます。 これらの人は、請負なり売買なり建物の契約に関しては消費者とは第三者となりますので、第三者としての不法行為責任となります。 このように、さまざまな人々の責任を問うことができますが、これらの人々の責任はどのような関係にあるかというと、本来は各人ばらばらにそれぞれが消費者に対して同じ責任を負う、つまり相当補修費用や関連費用を負担しなければならないのですが、二重取りはできないということで、法律上はこれらは 不真正連帯債務 と呼ばれます。 |
|||
3 その他の法律の根拠で相当補修代金の損害賠償を求められるか。 |
|||
契約当事者である請負人や売り主の業者に対して瑕疵担保責任と同じ内容の責任を求められるか というように考える場合と、同様の内容の 責任を業者以外の者に対しても求められるか という場合とに分けて考える必要があります。 契約当事者である売り主や請負人に関しては、昔は、瑕疵担保責任は民法の特別な規定であって、請負人の故意または過失によって手抜きされた場合の債務不履行責任が求められる場合でも、瑕疵担保責任に限定されるという 瑕疵担保責任特別法説 が有力でした。 そしてまた、一たんでき上がった建物は契約を解除することができないという民法 635 条を根拠に、契約の解除とは家は返し代金を戻すことで、 取り壊し建てかえ は代金の返却に取り壊し代金も含むのでできないという見解が有力で、この取り壊し建てかえ請求をすることができないという民法 634 条の瑕疵担保責任の解釈が制限されていたのに、法律制定当時とは違った手抜き社会が出現したいま、例えば地盤補強や基礎、建物の骨組みに故意の手抜きがあって、取り壊し建てかえをしなければ補修できない場合でも取り壊し建てかえ請求ができない、乃至 取り壊し建てかえ請求相当の損害賠償金の請求はできないというのであれば甚だ不当であるという見解も生まれ、民法 634 条の瑕疵担保責任にかわる法律の根拠規定として 債務不履行責任 、つまり契約上の債務の本旨に従った履行をしないものとして、それによって生じた損害賠償の請求ができるという債務不履行責任についての民法 415 条のこの条項を適用しようという説が有力になり、現に最近、最高裁が取り壊し建てかえ相当損害の責任を瑕疵担保責任と認めるまでは、この説によって取り壊し建替え損請求ができると主張されていたのです。 不法行為責任 についても同様です。 本来、不法行為とは契約関係のない人(第三者)が他人に対して損害を与えた場合の責任のことで、例えば車の運転者が歩行者を傷つけるといった場合の責任などが当たりますから、契約関係にある者同士では、不法行為責任を適用するというのはためらわれていました。 しかし、骨組みや基礎などの構造の手抜きによって、家の注文者や同居人、その家に出入りしたり付近を歩行している人に災害によって危害を与えるおそれがある場合、それは建築関係者なら当然心得ていることなのにあえてしもそのような手抜きをする場合、つまり他人に対する危害について未必の故意を有すると考えられる場合には、たとえ契約当事者であっても不法行為責任が成立するのだ、つまりひどい手抜きは契約という枠を超えて、注文者に対して財産上も精神上も危害を与えるという犯罪的意図が秘められているものなのだという構成のもとでこれを認める見解も有力なのです。 いずれにせよ、最高裁判所が民法 634 条の瑕疵担保責任の内容として取り壊し建てかえ相当損害の請求を認めるということを打ち出したことから、債務不履行責任や不法行為責任を積極的に持ち出さなくても、瑕疵担保責任の規定でこのようなケースの問題解決ができるようになったので、今後は債務不履行責任や不法行為責任を適用する場合は少なくなるものと思われます。 瑕疵担保責任の場合は、欠陥があれば請負人や売り主に対して、その人の故意過失に基づくものでない全くの無過失、例えば素人の消費者が転売した場合にも適用それるのに対し、債務不履行や不法行為の場合は請負人や売り主にその欠陥についての故意または重大な過失があることを要求され、消費者はその立証に手間がかかるからです。 次に、前項で述べた請負人や売り主といった 直接の契約当事者以外でも責任を求めなければならない者に関しては、契約上は第三者なので、瑕疵担保責任と同じ内容の責任は求められるかという問題があります。 適用される法条はもともと瑕疵担保責任ではなく、不法行為責任(民法 709 条)になりますが、損害賠償責任については同様の内容と考えてよいでしょう。業者本人とは不真正連帯債務の関係にあると上述したとおりです。 なお、ご参考までに、使用者の不法行為責任(民法 715 条)という規定もあります。 例えば住宅会社の建築士が設計や工事監理に関して故意または過失があったことによって欠陥が発生した場合には、その建築士を雇用する会社の上司または会社自体が同じ責任を問われることもあるのです。 |
|||
4 いつまで責任を求められるか。 |
|||
瑕疵担保責任にはいつまで求めることができるかというのが 時効 の問題です。 民法 638 条1項では、請負契約の場合は、鉄筋や鉄骨造の堅固な建物については引き渡しのときから 10 年間、堅固でない木造などの建物については5年間と定めています。 売買の場合は、買い主である消費者が欠陥を知ったときから1年間に限られています。 ただし、瑕疵担保責任は民法 639 条によって 短縮の合意 をすることができるとされていますので、請負契約による注文住宅の場合でも2年ないし1年に短縮されているのが通常ですが、平成7年の阪神大震災の際、手抜き欠陥が多く発見され、このような短い時効期間ではなかなか構造欠陥が発見できないということで、平成 12 年に制定された 住宅の品質確保の促進等に関する法律 では、売買(建売)でも欠陥の補修の請求を認めるとともに(請負の場合同様に、瑕疵担保責任としては現実の補修の請求と損害賠償の請求ができることとされたとともに)、新築住宅では、請負であれ売買であれ引き渡されたときから 10 年間は瑕疵担保責任が問えるとされたのです(住宅品確法 87 条)。 ただし、それは住宅のうち 構造耐力上主要な部分 と 雨水の浸入を防止する部分 に限られています。 つまり、これは従来手抜きが横行していた、すぐには消費者にわからない部分で、しかも住宅の本質を害する悪質な手抜き欠陥の部分を指しているのです。 |
|||
5 交渉するときの注意。 |
|||
①残代金の差しとめ |
|||
|
|||
②見切りが大切 |
|||
|
|||
③工事中の補修交渉と工事の差しとめ |
|||
|
|||
6 交渉以外の請求手続。 |
|||
| ①調停 | |||
|
|||
②仲裁 |
|||
|
|||
③訴訟 ( 裁判 ) |
|||
|
|||
7 相当な補修方法とは。 |
|||
①設計図書への適合性 |
|||
|
|||
②技術的可能性 |
|||
|
|||
③施工の確実性 |
|||
|
|||
④近隣等第三者への損害・迷惑に対する配慮。 |
|||
|
|||
⑤経済性。 |
|||
|
|||
8 補修にかわる賠償金額はどのようにして算定するのか。 |
|||
①見積もりと損害評価の違い。 |
|||
|
|||
②業者の仲間値ではなくて消費者の小売値で。 |
|||
|
|||
③算定基準としての相当な資料。 |
|||
|
|||
| 欠陥住宅正す会の相談会は、複数の法律に詳しい建築士と建築に強い弁護士とが共同して、問題解決まで繰り返しくりかえしご相談に応じ、きめ細かい対策をたてています。又、体験者の体験指導も行っています。 欠陥住宅でお困りの方に当会のご紹介をお願い致します( 詳しくは事務局まで 大阪 06-6443-6058 、 東京 050-8003-5039 ) 。 | |||