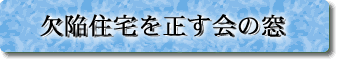|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和53年以来24年に亘って欠陥住宅被害者救済活動を続けている
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -正す会の窓・・・その16(論説)- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欠陥住宅紛争対策をめぐる新しい流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 阪神大震災後 欠陥住宅を正す世論の高まりの中で、法制面でも裁判上も新しい流れがみられるようになりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欠陥住宅紛争対策をめぐる新しい流れ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 次
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欠陥住宅紛争対策をめぐる新しい流れ ( 続欠陥住宅紛争の実情と問題点 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.住宅の生産システムの変遷と欠陥住宅の登場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昭和 35 ~ 36 年までの大工、棟梁と消費者との直接施工による住宅生産システムにかわり、集客を主目的とする 住宅会社による重畳的住宅生産システム の登場によって、請負人と生産者は分離し直接受注による信頼関係がなくなるとともに、各下請における必要利潤の捻出のために生産原価の切り下げを余儀なくされたことから、いわゆる 手抜き欠陥 が発生し 「欠陥住宅」 という言葉が生まれた。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.阪神大震災を契機とする積極的な欠陥住宅施策の登場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欠陥住宅問題は、昭和 40 年代の都市人口の増大、農村・都市を問わないコミュニティーの崩壊に伴ってますます増大し、社会問題化するに至っていた。 そこで、昭和 40 年代末期には、「プレハブをよくする会」「マンション問題を考える会」など主として関東で集団的交渉による欠陥住宅対策を考える消費者団体が生まれた。 この動きには、同時代のアメリカにおけるラルフ・ネーダーの欠陥車追放運動も影響を与えていると思われるが、これらの団体には、マンションやプレハブなど同じ類型の建物を持つ共通の被害者で組織しようという点に特色があった。 しかし、住宅、特に戸建て住宅は、極めて個別的な地質、地形の土地に立脚する個別性の高い契約によってなされるため大衆団交方式による解決には親しまず、新たに、住宅の個別契約性及び専門技術性に着目した主として 戸建て住宅の被害者によって組織される消費者運動 が勃興し主流となるに至った。 そして、各種行政窓口や消費者センターに欠陥住宅の苦情が殺到する状況に至り、昭和 54 年ごろからはテレビ、週刊誌を媒体とする欠陥住宅報道が巷間をにぎわすにようになった。 ただし、救済の決め手となる欠陥調査・鑑定の方法や専門家は数少なく、解決の決め手となる民事訴訟手続も裁判所、弁護士ともに不馴れで、技術訴訟というよりは事情訴訟の観を呈し、 裁判をすれば金も時間もかかるだけだと言われた時代 であった。 しかし、平成7年の阪神大震災はこの欠陥住宅問題をより社会問題として顕著化させ、それに対応して国家による各種施策が積極化した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.住宅品質確保法の登場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅品質確保法については既にご承知のとおりで多言を要しないが、平成 11 年に登場した本法は、欠陥住宅問題発生の根元を契約される住宅の品質内容の不特定にあることに着目し、住宅の品質の特定可能な項目の性能をそのレベルでとらえることによって、可及的に品質特定を図ることを目指している。 これは、従来の住宅の品質の特定が目視等の五感で把握できるいわゆる 不具合事象 に頼っていたのに対し、住宅の品質を 性能とそのレベルでとらえる ことによってより特定性を高めたもので、その具体化が 日本住宅性能表示基準 である。また、欠陥住宅発生予防のために、この表示基準をもとに 設計住宅性能評価 と 建設住宅性能評価 の制度が定められ、少なくとも建設住宅性能評価を得ている建物については、前提となっている設計住宅性能評価書が特定する品質を有するものと見ることができるシステムとして確立された。 しかし、これらはあくまでも請負・売買双方の契約当事者の任意の手続にるものである。 また、平成 13 年には 既存住宅性能評価制度 も定められ、既存の住宅についても目視及び簡単な計測によってある程度の品質を専門家により推測し、既存住宅の流通に役立てる制度が考案されたが、この既存住宅性能評価手続も契約当事者の任意申請に基づく手続である。 そして、この手続によったいわゆる 評価住宅 については、住宅紛争審査会による簡易な紛争解決手続が可能になるに至ったことも周知のことである。 これに対し、同法に基づく性能評価手続を受けていない住宅をも含め、平成 12 年4月以降に契約かつ新築された住宅については、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分について 瑕疵担保責任 の 10 年間の存在が強行法規化された。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.裁判所部内における欠陥住宅紛争対策 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裁判官はもともと文系の出身者であり、技術問題に関しては知識とともに感覚的にこれを忌避する傾向があった。 また、民事手続の当事者代理人となる弁護士も同様で、欠陥住宅問題に関しては全くお手上げといった状態で、専門家である業者側がひとり独自の見解を主張し、クロとシロにとまではいかなくとも、灰色と言いくるめて、消費者側の賠償請求を阻止してきた。 多くの欠陥住宅訴訟では 欠陥の意義 すら明確化されず、 欠陥現象または不具合事象と欠陥原因との区別、欠陥判断の基準、相当な補修方法、損害賠償の範囲 と 金額 、裏返せば相当補修工費の算定方法等については、全くと言っていいほど 空白の時代 が続いていた。 技術訴訟でありながら、多くの訴訟では契約に至った経過にまでさかのぼり、当事者の約定不履行、不誠実な対応など怨嗟を含む感情的な事情訴訟に終始し、それとともに、「設計図書」等の非日常的な建築用語が登場するので、千日裁判の様相を呈し、前述のように業者側がひとり満足する結果となっていたのである。 これに対し、阪神大震災を契機としてより社会問題化した欠陥住宅問題、特に難渋を極めている欠陥住宅訴訟制度の対策として、裁判所部内では任意の制度として、正式裁判(民事訴訟手続)を裁判所の職権によって民事調停手続に移させるいわゆる 移付調停の制度 が運用としてとられるに至った。 そのねらいは、建築士など建築専門家を調停委員に選任することによって、裁判官の技術的知見の不足を補い、欠陥問題についての当事者の言い分を整理して、争点を技術的、法律的に明確化するところにある。 もとより調停手続であるので、専門家調停委員による相当公平な調停あっせんの努力も行われるが、当事者がこれに同意しない場合は通常訴訟に移行し、調停手続中における調停委員による争点整理と裁判官に対する技術的知見の事実上の補充を最大限に活用するという制度である。 また、平成 13 年には東京と大阪に 建築専門部 が新設された。 これは欠陥住宅を含む建築事件を特定の専門部に処理させることにより、裁判官をして欠陥問題の処理方法並びに法律知識を通暁させることをねらったものである。 ここでも移付調停が活用され、紛争の多くは調停手続によって解決される結果になるとともに、欠陥類型によって一定の相当補修方法や賠償金額が類型化され、後発の事件処理に役立てられている。 さらに、平成 14 年には 民事訴訟法が改正 され、新たに 専門委員の制度 が設けられた。 技術的知見を要する事件について、裁判所が建築士などの専門家から専門委員を任意選任し、裁判官の技術的知見を補うとともに、争点整理にも参加させ、当事者に質問し、また証人尋問手続においても発問する権利を有するものである。 移付調停が調停制度の運用による任意の裁判所に対する技術的知見の補充方法であったのに対し、専門委員は法律によって積極的に訴訟手続に関与できる専門家の登場を認めたもので、この活用によってさらに欠陥住宅訴訟の進展が図られることになろう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.建築基準法の改正 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従来から同法には、 計画段階からの設計図書の法適合性の確認 、また 施工途中における諸検査の制度 がとられ、同手続上の 工事監理者 には所定資格の建築士を選任することによって、少なくとも建築基準法令違反の欠陥住宅が生まれないシステムがとられてはいたが、建築当局者の人員不足や建築士の名義貸しなどさまざまな脱法行為によって、同法の手続は骨抜きにされていた。 そこで、阪神大震災を契機にその運用をより厳正化ならしめるため、いわゆる 中間検査の強化 や 建築基準法の単体規定 においても筋交いの梁との緊結方法の技術基準をより具体化することなどによって同法の解釈の画一化を図り、より一層 欠陥住宅の発生を防止する法律改正 がなされた。 しかし、いかなる法令強化がなされようとも、当事者が遵法意識を高め、特に建築士が工事監理の重要性、つまり工事監理者が欠陥住宅防止に果たす役割を自覚し、また建設業者が施工技術確保義務を尽くす努力をしない限り、欠陥住宅は完全に防止できないものである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.消費者サイドに立つ最高裁判所判決の登場 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上、①から③の 各判例の流れを整理 してみるならば、端的に言えば、今まで民法上の形式的な条文の解釈論で責任を否定してきた消極説に対し、欠陥住宅の多発を前に実際的な根拠から責任を認める積極説に軍配が上がったものである。 しかも、その根底には、単なる民法の条文の形式的な文言解釈だけでは結論が出ず、さきに述べたように、契約者と施工者が分離する重畳的下請システムによる 住宅の生産システムの変化 と、これによる考えられないような ひどい手抜き欠陥の出現 という民法制定時の 100 年前とは異なる社会実態の変化と、従来は素朴に建っていて使えればよいとして不具合事象の有無だけで住宅の品質を判断していたのに対して、今建っているものでも一定の地震や台風に遭遇すればつぶれることもある。 そのような場合でも法定限度の強さの荷重や外力によるものであれば耐えられるだけの性能を持っていなければならないというように、不具合事象が現存するか否かではなく、 建物の品質を性能でとらえ、法律で、または社会的に是認されている最低限のレベルの性能を持っているかどうか で欠陥を見ていくというように、建物の品質のとらえ方が変わったことなどの実質的な根拠を考えれば、もはや消極説は成り立たないことが一般的に受け入れられるようになってきたことによるものと言える。 なお、これら最高裁の判例は、新立法にも匹敵するもので、今後手抜き業者に対する制裁はますます強くなっていくものと見るべきであろう。 このように、 欠陥住宅をめぐる法制度や裁判例などの法的環境は激変 した。 従来は、ともすれば民法の形式的解釈から出発し、生産者である請負人も注文者である消費者も法律上対等であることを理由に、その前提で公平論が立てられてきた。 その結果、その公平はむしろ社会的、経済的、専門知識的に劣者である消費者側にリスクがかぶせられることになっていたのである。 これに対し、縷々述べたように、社会の実態、住宅の生産システムの変化や住宅の品質のとらえ方の変化によって、 従来の形式的法文解釈から実質的な消費者救済の流れへと変化 したものである。 思えば、民法自体が 100 年前に制定されたものではあっても、借地借家法や労働三法などの住まいづくりのほかの領域では、契約当事者の実質的強弱を考慮した特別立法がされることによって社会的な不公平が取り除かれてきていたのに、住宅に関してはこのような特別法がないために、さきに述べた諸点についても法律の文言解釈に終始する消極説が一人歩きをしてきたのである。 住宅に関しては、特別法で新立法はされていないけれども、これらの最高裁の判例が出たことは新立法にかわるものとして積極的に評価されるものである。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.今後の展望 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上のような欠陥住宅対策の諸施策や最高裁判所の消費者サイドの判決が出たからといって、現在我が国において展開されている住宅をめぐる紛争、いわゆる欠陥住宅問題が解決するというものでもなく、また欠陥住宅をめぐる法律上の争いもすべて解決したというわけではない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欠陥住宅正す会の相談会は、複数の法律に詳しい建築士と建築に強い弁護士とが共同して、問題解決まで繰り返しくりかえしご相談に応じ、きめ細かい対策をたてています。又、体験者の体験指導も行っています。 欠陥住宅でお困りの方に当会のご紹介をお願い致します( 詳しくは事務局まで 大阪 06-6443-6058 、 東京 050-8003-5039 ) 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||